2022.Feb.16
REPORTSトラウマとジャーナリズム:寄り添うとは?公正な言論空間の構築を目指して
―河原理子氏(東京大学大学院情報学環特任教授)のインタビュー―
[佐野]
これまでのご経歴と現在のご活動について教えてください。
[河原]
 2020年春まで、37年間、新聞記者をしてきました。1983年に大学(東京大学文学部社会心理学科)を卒業して、朝日新聞記者になりました。
2020年春まで、37年間、新聞記者をしてきました。1983年に大学(東京大学文学部社会心理学科)を卒業して、朝日新聞記者になりました。
社会部記者が長かったのですが、性被害の取材をきっかけに、事件事故や不慮の出来事で家族を亡くしたり、ご自身が被害にあったりした人たちを訪ねて話を聴くようになりました。それは1990年代のことで、当時は被害者が知らないうちに刑事裁判が進行することがあるなど、聞いて驚くことばかり。刑事司法制度の中で置き去りにされていた被害者の状況を中心に記事を書き、書くそばから制度は変わっていきました。ちょうど日本で被害者支援が少しずつ広がる時期で、多くの人から学ばせていただきました。
そのなかで、私自身の宿題として残ったテーマが、「被害者と取材・報道」でした。集団的過熱取材への批判がある一方で、「なぜ私たちの話を聞きに来なかったのか」という声もあって、どうしたらよいのか悩みました。まずは取材された側の経験を聴くことが必要だと考え、地下鉄サリン事件のご遺族である高橋シズヱさんと一緒に2000年から2011年まで社外で、有志の記者たちの勉強会を開きました。記者が聞きたいことに答えてもらうQ&Aではなく、被害者やそのご家族がほんとうにどういう体験をしたのかを、まず語っていただいて、嫌な取材・報道や良い取材・報道があれば、具体的に教えてもらいました。
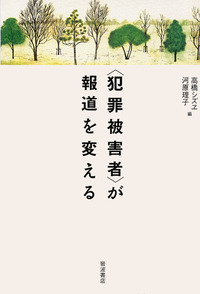 ここで身を正されるような思いをして、中間報告として、2005年に『〈犯罪被害者〉が報道を変える』(岩波書店)という本にまとめました。さらに誰かが深めてくれるといいなあと思ったのですが、そう都合よくは進まず(笑)。私自身も、新聞社にいる間は慌ただしくて、新しい知識を吸収する時間が少なかったので、退社した後、「聴く」ことについて学び直したり、外国の取り組みをリサーチしたりしています。情報学環教育部で授業する機会をいただき、受講生とのやりとりからもヒントをもらっています。
ここで身を正されるような思いをして、中間報告として、2005年に『〈犯罪被害者〉が報道を変える』(岩波書店)という本にまとめました。さらに誰かが深めてくれるといいなあと思ったのですが、そう都合よくは進まず(笑)。私自身も、新聞社にいる間は慌ただしくて、新しい知識を吸収する時間が少なかったので、退社した後、「聴く」ことについて学び直したり、外国の取り組みをリサーチしたりしています。情報学環教育部で授業する機会をいただき、受講生とのやりとりからもヒントをもらっています。
[佐野]
おそらくそのご活動のひとつの位置づけかと思いますが、B’AIグローバル・フォーラムで座長を務められているTrauma Reporting 研究会について教えてください。
[河原]
 『Trauma Reporting: A Journalist’s Guide to Covering Sensitive Stories』(2019)という本を、まず読んでいます。新聞社や放送局の取材者とジャーナリズムなどの研究者と一緒に、各章を読んで報告し、それぞれの経験をもとに話し合っています。
『Trauma Reporting: A Journalist’s Guide to Covering Sensitive Stories』(2019)という本を、まず読んでいます。新聞社や放送局の取材者とジャーナリズムなどの研究者と一緒に、各章を読んで報告し、それぞれの経験をもとに話し合っています。
この本は、イギリスの公共放送BBCで研修を立ちあげたJo Healeyさんがまとめたものです。トラウマティックな体験をした人に配慮しながら取材して、ジャーナリズムの使命を果たすにはどんな方法があるのか、取材された側の経験とベテラン取材者の実践をもとに、具体的に提言しています。研究者の協力で、トラウマについての豆知識も書いてあります。
事件事故、 (性)暴力や虐待の被害者、災害の被災者、その家族、戦争や紛争の生存者や目撃者など、心身にダメージを負ったvulnerableな(傷つきやすい)人たちから話をきいて伝えるには、知識やトレーニングが必要です。取材する側があらかじめ知っていれば防げることがあると私も思います。
「共感する」「寄り添う」ことが必要だと、報道の世界でも、ここ数年ますます言われるようになりました。しかしそれは、具体的にどうすることなのでしょうか。何をしないことなのでしょうか。事実の報道そのものが、誰かを苦しめることもあります。また、きちんと聞かずに「被害者とはこういうモンダ」という思い込みに基づいて描く、ステレオタイプな被害者像に沿った報道もあって、取材を受ける側に失望やストレスをもたらしています。
もっと中身を議論していかないと、「共感」も「寄り添い」も、耳障りの良いスローガンにすぎません。
この本の事例の多くは英語圏の出来事ですし、取材文化の違いもあります。けれどもそれを超えて、いままで私自身が現場でもがきながら体得してきたものが、言葉になっているという実感があります。研究会でのディスカッションを踏まえて、いずれなんらかの形で、もう少し広く共有できるようにしたいと思います。
[佐野]
「寄り添う」とはどういうことなのかを考えるのは、昨今のSNSによる中傷をいかに防ぐかとも共通する課題な気がします。
[河原]
その人の心情を想像せよ、ということでしょうか……。
想像したり、「もしも自分だったら」と考えたりすることで改善できる部分は確かにあります。その人の存在まで否定するかのような暴力的な言い回しは、そもそも相手のことを「ひと」とみなしていない、ということかもしれません。
ただ私自身が痛感してきたのは、思わぬ災難に見舞われた人の体験は、私の想像などはるかに超えている、ということでした。何を思うか、それからをどう生きるかも、人それぞれ違うし、同じ人でも時間の経過で変わります。そう簡単には、わからないのです。
 しかし世間には、「被害者はこうふるまうモンダ」「本当の被害者ならこんなことはしない」といった固定観念が根強くあります。実際の姿とは違うのに。そうした思い込みをもとに人を批判したり決めつけたりする類のものも見受けられます。(追記:傷つきやすい被害者の)現実の姿を、報道でももっと伝えていかないといけないのかもしれません。
しかし世間には、「被害者はこうふるまうモンダ」「本当の被害者ならこんなことはしない」といった固定観念が根強くあります。実際の姿とは違うのに。そうした思い込みをもとに人を批判したり決めつけたりする類のものも見受けられます。(追記:傷つきやすい被害者の)現実の姿を、報道でももっと伝えていかないといけないのかもしれません。
事件後に被害者がさらに傷つく「二次被害」は、当事者に接する誰もが加害者になる可能性があるのですが、そのなかで、かつては「近所の心無いうわさ」程度だったもののボリュームが、この数年、大きくなり、速い渦巻きになって人を脅かしていると感じます。「二次被害」というのは、事件事故そのものによる一次的な被害の他に二次的に受ける被害のことで、たとえば、捜査の過程で配慮のない対応をされるとか、周りの人たちから心無い言葉をいわれてしまうとか、取材報道によるものもここに含まれるのですけれども。いままでは知っている周りの人たちから受けてきたようなことが、もうすごく大きな渦になってきて、知らない人たちがいきなり自分の名前をWeb上に書いたり、心無いことをいわれたり、こいつは犯人に違いないとか決めつけられるなどでSNSによる二次被害が大きくなっていることはあると思います。
励ましの場合は悪気はないかもしれません。しかしながら、いつまでも泣いていてはだめとか、四十九日も過ぎたのにお子さんが浮かばれないわよとかいわれても本人にはどうしようもないことでもあります。そして、被害にあった人はいつまでも下を向いて、いつまでも泣いているものという役割を期待されて、そうではないとバッシングされたりもする。被害者のくせにとか、あんなことがあったのにとかいわれたり、民事裁判を起こすとお金目的ではないか、人の命を金にかえてとか陰口を叩かれたりする。必ずしもみんなは優しくないし、生きやすくもない。ですが、そういった状況にいる人がどのような状態であるかをちゃんと知ることで、防げることがかなりあるように思います。
 警察にせよ、弁護士さんにせよメンタルケアに関わる人にせよ、様々な専門職として関わる人たちはここ20年ぐらいの間にかなり学びを重ねてきて、二次被害をできるだけ与えないような取組を重ねてきました。しかしながら、ジャーナリズムや取材をする業界の人たちは、私からみれば、知っていれば防げることがかなりあると思います。例えばトラウマを抱えた人の反応についてあらかじめ知っていれば、目の前の人が必ずしも泣きながら話すわけではない、感情が凍結してしまって話せなくなることもあるし、後から具合が悪くなることもある、そういうことを知っていれば防げるし、追いつめるような聞き方をしないでしょう。まったく自分に理由がなくても自責感が強い人が多いので、そういう聞き方を避けるというのもあります。そのような知識をもっていれば防げることがかなりあるのに、ジャーナリストの世界ではまだ十分に知られていない、そんな現実があるように思います。
警察にせよ、弁護士さんにせよメンタルケアに関わる人にせよ、様々な専門職として関わる人たちはここ20年ぐらいの間にかなり学びを重ねてきて、二次被害をできるだけ与えないような取組を重ねてきました。しかしながら、ジャーナリズムや取材をする業界の人たちは、私からみれば、知っていれば防げることがかなりあると思います。例えばトラウマを抱えた人の反応についてあらかじめ知っていれば、目の前の人が必ずしも泣きながら話すわけではない、感情が凍結してしまって話せなくなることもあるし、後から具合が悪くなることもある、そういうことを知っていれば防げるし、追いつめるような聞き方をしないでしょう。まったく自分に理由がなくても自責感が強い人が多いので、そういう聞き方を避けるというのもあります。そのような知識をもっていれば防げることがかなりあるのに、ジャーナリストの世界ではまだ十分に知られていない、そんな現実があるように思います。
研究会はいまのところは書籍を読んでいるだけですが、何らかの形でこれを日本でも共有できるようにすれば、それだけでもこの状況を改善するために前進ができるかな、という気がします。
人の意識を変えるのは簡単ではなく、ある意味では恐ろしいことですが、多数の意識に働きかける方策も考えなくてはならないでしょう。
[佐野]
ジャーナリストがvulnerableな(傷つきやすい)人たちを取材するスキルを取得することが、B’AIグローバル・フォーラムが目指す公正な言論空間の形成にどのようにつながるのでしょうか?
[河原]
「スキル」というより、向き合い方として私はとらえていますが、ともあれ、トラウマティックな経験をした人の特性を理解して、取材者としてその人たちに接するときのより良い選択肢を知ることが、なぜ大切か。消極的な理由としては、二次被害をできるだけ及ぼさないようにするため。ですが、もうひとつ積極的な意味としては、偏見や固定観念を持たれやすい、話すことが難しい、あるいは声が届きにくい人たちの話をきちんと聞いて社会に伝える、もしそこに課題があるなら、整理して社会に示す必要があるからです。その回路を、もう少し確かなものにしなければなりません。偏見や固定観念を少しでも崩していかないと、何かの法制度はできたとしても、当事者の生きにくさは続くのではないでしょうか。
私が犯罪被害者支援の取材を始めたころ、私のなかに生まれた疑問は、「なぜ、日本で、被害者の環境整備はここまで遅れてしまったのか」ということでした。ハンセン病や強制不妊手術の問題にも、似た側面があるのではないでしょうか。
 女性の声や経験が日本社会で活かされにくいという問題は、意思決定の場に女性を増やすことで、ある程度は改善できるかもしれません。女性は社会全体では少数派ではないので、意思決定の場にも増やすことはできるはずです。けれども、そもそも少数であったり、見えにくかったり理解されにくかったりする人たちがいます。
女性の声や経験が日本社会で活かされにくいという問題は、意思決定の場に女性を増やすことで、ある程度は改善できるかもしれません。女性は社会全体では少数派ではないので、意思決定の場にも増やすことはできるはずです。けれども、そもそも少数であったり、見えにくかったり理解されにくかったりする人たちがいます。
それまで世の中に流れてきた言説に偏りがあるとき、もしAIで世の中の言説を取り込んで何かを構築しようとすれば、偏見や固定観念を再生産することになるでしょう。その偏りは是正しなければなりませんし、取り込む過程で是正するよりも前に、まず言論空間をより公正なものに近づける努力をしなければなりません。Trauma Reporting 研究会は、公正な言論空間をつくるための取り組みの、ひとつなのだと考えています。